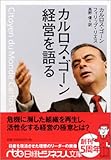Ecole d'ingenieursのランキングについては、「技術系のグランゼコール」で紹介しましたが、今回はEcole de commerce(商業系のグランゼコール)のランキングについて紹介しようと思います。ランキング付けの方法については、「技術系のグランゼコール」で紹介した手法と同じです。グランゼコールと言うのは、基本的には理工系が多いです。これは、グランゼコールがフランス革命後に必要となった技術者を養成するための学校としてスタートした歴史に由来するものです。時代の変化により、経済におけるエリートの必要性から商業系のグランゼコールも誕生してきました。
Palmarès des grandes écoles - Le point(グランゼコールの上位リスト)
関連:
技術系のグランゼコール
Read More ...
現在、名門とされる国立のグランゼコールの多くは18世紀に設立された。こういった歴史の古いグランゼコールの殆どが理工学関係の技術者の養成機関である。これは、フランス革命によって貴族制が否定された後、新しく国家を再建する際に必要な人材(理工系の技術者)が求められていたのにも拘らず、当時におけるフランスの大学は職業訓練校としては適切に機能しておらず、そういった分野の人材育成機関を国家が自ら用意する必要があったためである。(wikipediaより)では、上位10校の商業系のグランゼコールを見ていきます。
Palmarès des grandes écoles - Le point(グランゼコールの上位リスト)
- HEC(HEC経営大学院)
HEC経営大学院は、ビジネス・スクールであり、フランスのグランゼコールの中でも名門校の一つである。1881年にパリ商工会議所によって建学された。2005年以降、フィナンシャル・タイムズの欧州ビジネス・スクール・ランキングにてトップ・ビジネス・スクールとして評価されている。(wikipediaより)
論評は執筆中(LePoint.frより) - ESSEC
我々のランキングでは2位、ESSECはHECと並んで引き続きその他の競合を突き放した。この学校の強大な競争力:企業の人々と特権的な結びつき。14の教授陣、約250の研修所、潜在的な起業家のために個人の好みに合わせた随行:学生は即座にプロフェッショナルな環境に浴する。さらに、彼らの方式”アラカルト”は生徒に思い通りの課程を構成することを許す。国際化の面では、ESSECは最近シンガポールにキャンパスを開設した。提携校はどれも質が高く(半分以上は国際的である)、7つあるダブルディグリー提携校も同様である(中にはアジアでNo.1のMBAと考えられているインドのIIM AhmedabadやメキシコのEGADE-TEC de MonterreyやドイツのMannheimが含まれる)。唯一窮屈である点:”MBA”に最も名高い”グランゼコール”というプログラムと命名したことによる誤解の可能性。結論:この素晴らしい学校は、ライバル校のHECを輝かせたフィナンシャル・タイムズのように、数々の国際的ランキングにおいて忘れ去られているか、ペナルティーを科されているように見える。修了者は平均年間39,000ユーロで雇われ続けるなど、軽い曖昧さは雇用主を混乱させることは無い。名声あるこの学校のブランドは危険を伴う戦略によって保たれる...(LePoint.frより) - ESCP-EAP
素晴らしい職業的編入、活発な研究(終身教員の76%は博士号取得者)、卒業生の強力なネットワーク、国際的認知:ESCP-EAPは決定的に巨大な勢力を保持する。しかし、その独創性を見せる海外に開設されたキャンパスに設立された方式だ。学校は5つ運営される:もちろんパリであるが、11区の中心にあってさえそれは最も快適なわけではない、ロンドン、マドリッド、ベルリン、トリノ。この学校はまた、生徒に対してパリの課程(授業はたくさんの同じキャンパスの外国人と共に受け、交流の可能性を分かち合う)と、« nec plus ultra (これ以上の物はない)»ヨーロッパ課程の選択を与えている:3年間は3つの異なるキャンパスで3つまでディプロムを取得することを認めいている。結論:ESCP-EAPの44%の生徒(フランス人と外国人合わせて)が出身国以外の国で最初の職業に就く。記録である。(LePoint.frより) - Edhec
野心的だ、EDHECは今後、3つのキャンパスを設置することになっている:もちろんリール、そこはこの学校の起源で2010年を予定する新しい建物を建設中である、ニース、たくさんの外国人学生を受け入れる場所、そしてパリ。この学校は2006年1月から首都で”ヨーロッパ”研修(学校ー企業での24ヶ月の課程のうち4ヶ月の海外での課程)の方式を開発している、これは2005年ー2006年になされた我々のランキングには無かったことである。我々のランキングで、この学校は、教育の質、研究の質と共に海外のプログラムによって頭角をあらわした。全ての学生は最短で6ヶ月間は外国に出て、彼らの90%は1年間の区切りを利用することが含まれている、1年間の区切りを利用すると最短18ヶ月の期間である。この学校は常に、ESSECと並んで、最もお金がない学生に対して奨学金にによって補う試みの欠如によって、最も授業料の高額な学校である。学費/質の報告はおおむね肯定的である:この卒業生は、管理の学校で最も高く評価され、給料をもらえ、少なくとも学校の公表を信じる。メモ:EDHECは学生のうちいくらかを泊まらせることができる(リールの平均が1m^2で15ユーロであるのに対し、1m^2を11ユーロで利用可能な400の部屋)。価値は非常に確かだ。また、リールはまったく美しい町で、同様に歓迎的雰囲気である。(LePoint.frより) - EM Lyon
確かな価値、長い間品質補償されて来た(1998年のEquis、2005年のAACSB)、EM Lyonは質の高いアカデミックな体制で秀でており、研究は起業、市場のファイナンスやマーケティングの研究において名高い。”アラカルト”方式の教育は生徒に対して複数の選択を許し、外国文化の発見は特に推奨されている。ディプロムを取得するには3カ国語が必須であり、生徒は最低6ヶ月は外国で過ごす必要があり、平均18ヶ月は外国で過ごす(企業研修を含む)。この学校は、イタリアのBocconiやスペインのInstituto de EmpresaやカナダのHEC Montréalなど、海外の学校と数々の業務提携に同意して来た...学校は2007年に、ESCプログラムの全ての学生に精通させるため、中国にキャンパスを開設した。また、この学校は、1年目のに早速の学生の個人プロジェクトを作るのを支援する大きな努力をしている。監査とコンサルタントと銀行が高額の給料水準で、卒業生の半分以上を雇う。メモ:リヨンの中心街から10分のところに学校は360部屋のの宿舎を提供する。(LePoint.frより) - Grenoble Ecole de Management
常に良い考えをうかがっている、この学校は常に移ろい大忙しである印象を与える。公式にはフランスにおける革新の管理運営のスペシャリストの一つと紹介されている。しかし、2006年に準備された学生にLMDに対応した”アラカルト”方式の育成を選択させるための学校の新しい教育の組織は、全てかもしくはほとんどの手順と選択の自由(全世界コースですら)を見せる(実際、一年間区切り)。公表されている学習時間に関わらず、雰囲気はむしろ、大きく開いた空間に酔って明るい灰色と黒色のコンクリートの大きな建物なかで、くつろいでおり、学生は様々なフランスでは珍しいハイテクの恩恵を受けている:デジタル図書館は100%、Wi-fi環境、ビデオ会議システム。遠隔の授業のプラットフォームは言うに及ばず、生徒がどの国に滞在していても常に学校にアクセスできるインターネットの仕組みが提供される。この環境は、例えば団体活動など、基盤にに関わりたい学生を起業家の気質へと活動的にすることを刺激する:”提携”と養成の約束を組み合わせることを認める”提携代替”という手順が存在する。この方式は公表を博している(しかし、滑走路から数キロのグルノーブルの状況は、相当なものだ):この学校はだんだん魅力的になっている、そしてその結果、さらに選択的になる可能性がある。(LePoint.frより) - Audencia-Nantes
数年前から、この商業学校は特別進学クラスの学生から引っ張りだこの学校のうちの一つになった、そしてそれは偶然ではない;2005年の卒業生の60%は卒業前に職を見つけていて、80%は卒業後2ヶ月以内に職を手に入れた。かれらの収入?小さなグループの授業(英語のいくつか)は非常に具体的に方向付けられていて、企業における1年間区切りは必須であり、学習期間を延長した多くの研修生は、しかしながら、労働の世界の真実の知識を得ることができ、全ての学生は海外に滞在する。ここに、AACSBとEquisの二つの評判を加えておく、学生達の追従はよく考えられていた。もっと?生活環境:素敵なキャンパス(たとえ生徒は宿泊できなくとも)、ナントの歴史ある中心からトラムで15分、フランスにおいて最も快適な町の一つ(Le point誌の最近のランキングを信じるなら)、海が遠くない...だれもが何年かここで過ごしたいと思うだろう。この学校の強みはファイナンスとマーケティングである。(LePoint.frより) - ESC Rouen
論評は執筆中(LePoint.frより) - Euromed
論評は執筆中(LePoint.frより) - Bordeaux Ecole de Management
真面目と同様に、特定の保守主義が名高い、EMボルドーは今日、”美しい眠り”というそのイメージを激しく払っている。2005年から校長のPhilip McLaughlinはヨーロッパのランキングEquisの後に、アメリカのAACSBの称号を獲得したいと考えている。彼は古典的な、しかし確定的な教育学を考慮に入れ、3年目だけマーケティング、ファイナンス、監査の専門化を行っている(さらに2007年からは人的資源)。この学校は教授陣の86%が博士号の取得者であり、ワインの管理からはじめる専門官の鑑定の中心を同様に持つ。この学校は同様に、国際連合によって全世界の責任について研究するために選ばれた。最後に、この学校は学生を容易に就職させる:2005年は学生の48%が卒業前に職を見つけた。多数の学生は監査、産業、中央銀行、ファイナンス、保険の職業に就いた。敷地が手狭になったため、この学校は2009年に全面的に引っ越す予定だ。新しい若者達?(LePoint.frより)
関連:
技術系のグランゼコール




 日本とフランスの,留学,研究,政治,経済,外交,歴史,文化について考える
日本とフランスの,留学,研究,政治,経済,外交,歴史,文化について考える